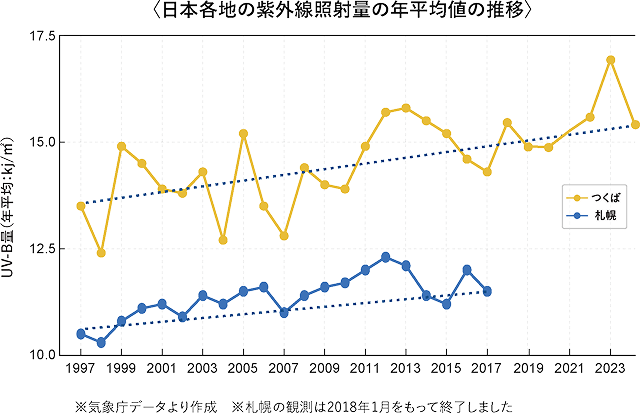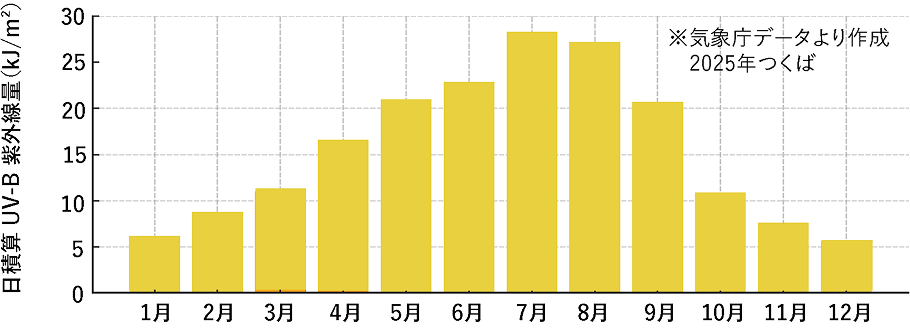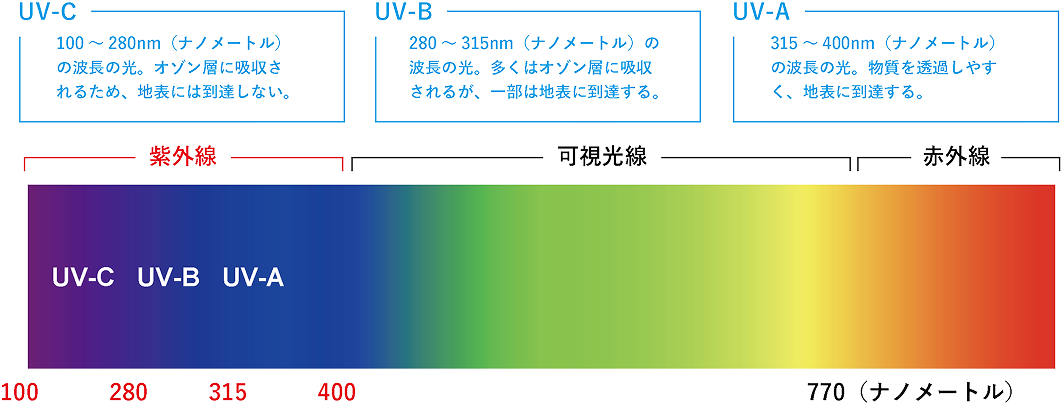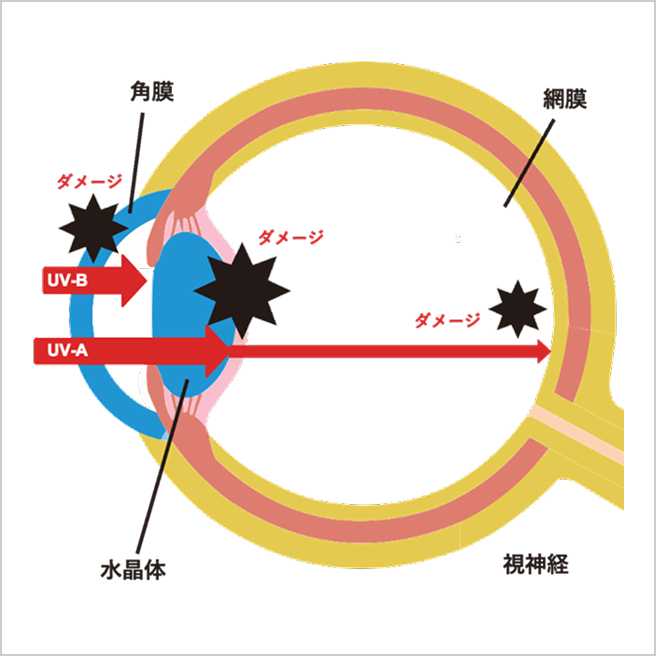活動実績


「めのため、未来のため」“強い日差しと紫外線”から目を守る習慣は部活シーンにも広がる

「めのため、未来のため」 中高生の目を“強い日差しと紫外線”から守る新たな習慣を
メガネブランドZoff「めのため、未来のため」中高生の目を“強い日差しと紫外線”から守る新たな習慣を